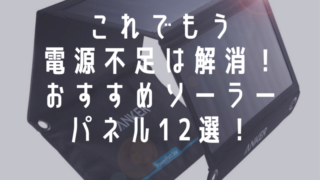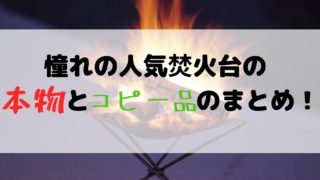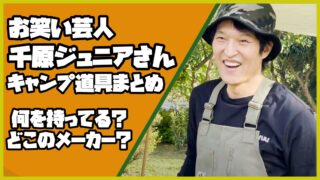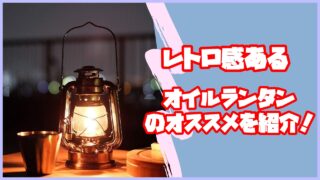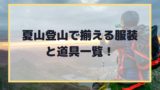登山は自然の雄大さや美しさを肌で感じることができる老若男女問わず人気レジャーですが、山岳遭難による事故が昨年(2022年)には過去最多になり増加傾向にあります。
2023年現在でも特に富山県、新潟県、長野県にまたがる北アルプスや山梨県、静岡県にまたがる富士山で遭難や滑落による重大な事故が人気の山々で多発しています。
今回はこれらの事故の根本的な原因や引き起こさない為にはどうすれば良いのかを考えていきます。
山岳遭難とは

山岳遭難とは、「山において生死に関わる困難・危険な状況に遭遇すること」を指します。
具体的には道迷い、滑落、転落、怪我、病気に加えて大雨や雪崩の急激な天候の悪化などで自力では安全に山を降りることができない状態に陥ることです。 最悪の場合は死亡するような大きな事故に発展するケースも度々見受けられています。
近年起こった山岳遭難による事故の例

24日午前11時50分ごろ、岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂の北アルプス・北穂高岳の稜線上にある長谷川ピーク(標高2841メートル)近くで、登山者の女性(44)から「人が滑落した」と110番があった。約2時間50分後、民間の山岳救助隊が稜線の約200メートル下で、50~60代とみられる女性が倒れているのを発見した。女性は県警ヘリで救助されたが、全身を強く打っており死亡が確認された。死因は多発外傷。
高山署によると、女性は1人で南岳から北穂高岳に向かっていたとみられる。身元の特定を進めている。
出典:yahooニュース
北アルプス仙人谷付近の標高約1700メートルの登山道で25日、68歳の女性が沢に転落、死亡しました。 警察によりますと死亡したのは、愛知県名古屋市に住む68歳の女性です。 25日午前7時35分ごろ、68歳の女性が友人の70代女性と、仙人池ヒュッテから阿曽原温泉小屋に向かう途中の標高約1700m付近の登山道で、約15メートル崖下に転落しました。
出典:yahooニュース
富士宮署によると12日午前2時27分ごろ、単独で富士登山をしていたとみられる男性から「足がけいれんして動けなくなった」と警察に救助要請が入った。 男性は富士山富士宮口7合目付近にいるとみられ、救助要請を受け警察官7名体制で現場に向かった。 富士登山は9月10日に終了、山小屋などの営業も終了し閉山している。
出典:yahooニュース
富士山への「弾丸登山」中に行方不明になっていた19歳のアメリカ人男性が、9月5日午前、無事救助された。
救助された時の映像を見ると、救急車に乗り込む男性の服装は、白いTシャツに黒いズボンと軽装だ。男性は救助後、笑顔を見せていたが、本格的な装備を持たない軽装で富士山頂を目指す「弾丸登山」をめぐっては、これまでもトラブルが相次いでいた。
富士山で「弾丸登山」をしていた外国人観光客2人が遭難したのは、4日午前4時半過ぎのこと。
出典:yahooニュース
事故が多発している原因

山岳事故の原因はさまざまですが、いくつかの主要な要因は以下のようなことで引き起こされます。これらの原因を理解し、適切な対策を取ることが安全に登山をするうえで重要です。
悪天候
強風、豪雨、霧、雷など天候の悪い状態での登山は事故のリスクが上がりやすいです。
ただ昔から「山の天候は変わりやすい」と言われるほど山は天候が急変しやすいので、天気サイトやアプリでは晴れでも現地では天候が悪い場合は撤退する勇気を持つことも大切です。
ルート選択の誤り
ルートを誤ったり、難しすぎるルートを選んだりすることで、登山者は道迷いや滑落などの事故のリスクに立たされます。
技術・知識不足
登山技術の不足や経験の浅さは事故の原因となります。特に標高の高いレベルに合わない難しい山では当然ながら事故に遭うケースは格段に上がります。
滑落による死亡事故の多い北アルプスは人気の登山スポットとして知られているが為に、初心者でも簡単に登れてしまうという誤った認識のまま登ろうしてしまいます。
他にも熊や猪といった野生動物と遭遇した際にも、適切な対処をしなければ襲ってくる可能性もありますので注意しないといけません。
必要な装備が不十分
適切な登山装備を持参しない場合、事故や怪我の危険にさらされる可能性が高まります。
特に富士山は「観光に来る山」「初心者でも登れる山」という間違った認識をされている人が多く、半袖、短パン、サンダルなどとても登山をするような装備をしておらず弾丸登山をしてしまうケースが後を絶ちません。
山は日中と夜間の寒暖差が激しく低体温症になるのできちんと防寒用の上着を用意しておくことや、足に疲労が溜まったり捻挫をしたりしないように登山靴やトレッキングポールを持っておくことが求められます。
単独行動
単独行動はで事故に遭った際には自分で何とかして助けを呼ぶしかなくなります。
山は携帯電話の電波が届かないことが多いので、自力で動けない重大な怪我をした場合は運よく電波が入るか、誰かがその場所を通るか、友人・家族が通報するかを祈るしか助かる方法はなくなります。
二人以上いれば誰かが事故に遭っても、残った人で助けたり、助けを呼びに行ったりできます。
事故を引き起こしてしまうマインド

事故を引き起こしてしまう人には以下のようなあるマインドが共通しています。
年齢による体力の低下を過信
昔は山をよく登っていたり、スポーツをしていた人が年齢を重ねても当時と同じ体力があると思って過信したことで事故を引き起こすことがあります。
人は年齢と共に確実に体力が低下していきます。そして普段から体を使っていない人はより体力の低下が著しいです。
「自分はまだまだ若いし大丈夫!」という油断した気持ちが、疲労困憊による遭難や体を支えきれずに滑落するといった命に係わる重大な事故に繋がります。
もちろん体力をつけるという意味で山を登ることもあると思うのですが、まずはランニングや筋トレで自分の体力レベルはどのくらいなのかを把握して、それから基礎体力をつけてから登った方が良いでしょう。
せっかく来たのだから何としてでも登頂したい
登山ではその日の天気予報は晴れでも山の天候は変わりやすく、現地では雨が降ったり風が強いなど天候に恵まれないことも多いです。
登山をする時は皆さん休みの日を使ってはるばる遠くから県を跨いだりして来ます。ただ、装備が適していなかったり、天候が悪くても「せっかく来たのだから何としてでも登頂したい!」と無理してでも登りたいという思いの人が強行してしまいます。
そのため、足元が濡れて滑落や視界不良で道迷い、寒くて低体温症になるなどの事故を引き起こしてしまいます。
難関ルートやタイムアタック自慢が流行
ネットが普及した昨今では、登山の楽しい思い出として自然の優美な姿やその時に感じた思いをそれぞれ一般の登山者でも自分の記録を投稿できる時代です。
ですが、中には難関ルートと言われる一歩間違えれば死亡事故に繋がる危険なエリアを何の技術や知識もなしに敢えて挑戦することや、山頂まで登って下山するまで一般的に2日以上かかる山に日帰りで挑むタイムアタックをする自慢をしている人が度々見受けられます。
以前は山小屋などでそのような自慢を聞く機会がありましたが、ネットの普及でより多くの人達に向けて発信したり、閲覧したりすることができるので、それに触発されてしまった人が誰かに認めてもらいたい一心で無謀な挑戦をするようになります。
登山で事故を防ぐためには

計画と準備
登る山のルートを誤らないように登山地図を持参したり、GPS対応の地図アプリを入れて事前に所要時間や、分岐地点、難所などの確認をしておきましょう。登山ブログやサイトなどで写真を見ながら確認すると尚良いです。
また天候は天気サイトやアプリがあるので、なるべく晴れ間が多くて風もない日に登るようにして下さい。
登山サイト・アプリは「YAMAP」、天気サイト・アプリは「てんきとくらす」がおすすめです。
適切な装備
適切な登山靴、防寒具、雨具、帽子、手袋、サングラスなどの装備を持参し、季節や地域に合った服装を選んでください。
また、登山用具(アイゼン、ピッケル、ハーネス、ロープなど)を必要に応じて持参し、正しく使えるように訓練を受けてください。
十分な食料と水を持参し、必要な場合にフィルターなどで水を浄化できる手段を持っていくことが重要です。
技術と経験
自分の技術と経験に合った山を選び、必要に応じてトレーニングをしましょう。
初心者は経験豊富なガイドや登山仲間と一緒に登山することをおすすめします。
また、アウトドア関連のツアーやクラブでは登山技術や応急処置についての講習や訓練を企画している所も多いので、されらに参加して身に付けることもできます。
グループで行動
単独登山は避け、できるだけグループで行動しましょう。仲間との連携が遭難時に生死を分けることがあります。
グループの一員が怪我をした場合、適切な応急処置を提供できるようにトレーニングを受けておきましょう。
グループで行けない場合はなるべく登山者の多い山や時期を選んでみて下さい。
健康状態
体調不良の場合は無理せずに休息や撤退など適切な行動をとりましょう。
無理を続ければ体調が悪化する可能性や助けを呼びにくい場所まで来てしまう可能性もあります。
特に毒を持っている動物に噛まれたり刺されれば、短時間で体に毒が回ってしまいますので早急に病院へ行くようにして下さい。
また、自分や他の人が体調が悪くなった時の為に応急手当の道具や薬を常備しておきましょう。
緊急事態への対応
万が一に遭難した場合、ライトを使ったSOS信号のやり方を知っておくことが重要です。
ライトのSOS信号のパターンは「・・・ — — — ・・・」短い点灯を3回(間隔をおく)長い点灯を3回(間隔をおく)短い点灯を3回します。
また、登山口に設置してある入山届に登山計画の記入や、出かける前に友人や家族に伝えて帰宅予定時刻を共有しておくことで、遭難してしまった場合助けを呼んでくれて命が助かることに繋がります。
事故を防ぐマインド

ポジティブよりもネガティブに考える
山登りを楽しみに来ているのにネガティブに考えるとは何だかおかしな感じがしますが、「体調が悪いけど最後まで登る!」「天候が悪いけどせっかく来たから登りたい!」「危険な道で道具もないけど行ける!」などのポジティブな考えは返って無謀な行動をとってしまい事故に繋がる恐れがあります。
逆にネガティブに「~が悪いからやめておこう・無理はしないでおこう」という考えの方が慎重で冷静な判断をしやすいので、事故を引き起こす頻度も減ります。
「山は逃げない」を頭に入れておく
大げさに聞こえるかもしれませんが、登山は一歩間違えれば命を落としかねないレジャーであることを認識しておかなければいけません。
現地に着いてから体調や天候などのコンディションが悪ければ、その日は登るのをやめようとする勇気も大切です。
「山は逃げない」という言葉があるように、時間さえあればいつでも再挑戦して山登りはできます。事故が引き起こさないように常にこの言葉を頭に入れておきましょう!
最後に
山岳遭難事故は過去にないくらいのペースで増加傾向にあります。このような事故を引き起こさない為にも山に入る行為は命をかけていることを常に意識して下さい。
「自分は大丈夫!」が命取りになります。
登山を計画する前に今一度無謀なことをしていないかを自分に問いかけてみて、足りない所はきちんと準備してから挑むようにすれば事故になる可能性は大分減るでしょう。